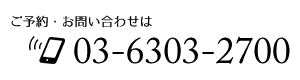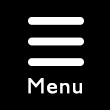ラミネートべニア法は、主に前歯を対象とした見た目の優れた治し方で、歯の表面を一層削って白い透明性の高いセラミックもしくはレジンシェルを歯に貼り付ける方法です。
では、どのくらい歯を削るかというと、おおよそ0~1.0mm程度の範囲内で、一切、歯を削らないこともあります。
歯をあまり削らないことにより、接着に非常に安定しているエナメル質を残すことができ、べニアの取れやすさを大幅に軽減できるようになります。
歯をあまり削らないと言っても、日本人の唇側歯頚部のエナメル質な非常に薄く、象牙質露出の危険があり注意が必要です。
私は、このラミネートべニアが40年ほど前にアメリカから導入された当初から、大学で研究を行い、学会発表や論文発表しながら臨床応用を続けております。
当初は、現在のようにMI(Minimal intervention=最小の侵襲)の考えも浸透しておらず、優れた接着性レジンセメントも登場しておりましたが、勤務していた大学内でもこれは「補綴ではない」、「被せるのが1番」というような、「そのうち消える治療法」として捉えられていた風潮があり、一般臨床家にとってはさらに「テンポラリーな治療法」と思われていた時代でした。
もちろん大学での学生教育にも取り入れられておりませんでした。
しかし、現在は当然のように審美治療法の1つの選択肢として存在し、学生の教科書にも掲載され、大学の授業や臨床実習の場でしっかり教育されております。
ではラミネートべニア(laminate veneer)修復について詳細に説明させていただきます。
補綴修復物の一つで、部分被覆冠に分類されています。
主に審美的な改善を目的として使用される薄いセラミックもしくはハイブリッド型コンポジットレジン製のシェルを接着性レジンセメントで装着する方法です。
薄くて美しい仕上がりが特徴で、審美的な改善に非常に効果的な治療法です。個々の患者のニーズに応じたカスタマイズが可能であり、歯をあまり削ることなく自然な外観を実現できます。
ラミネートべニアは、審美歯科の進化とともに発展してきた技術であり、現在も多くの患者に利用されています。
ジルコニアをはじめとする各種セラミック材料の進歩および接着材料や技術の進歩により、より自然で耐久性のある治療法としての地位を確立しています。
ラミネートべニアは多くの審美的な問題に対して有効ですが、適応症と禁忌症を理解し、適切な診査が行われることが大切です。
治療前に担当歯科医師と十分に相談し、あなたにとってそれが最適な治療法なのかを選択する必要があります。
では歴史について少し説明いたします。
歴史の概要
ラミネートベニアの起源は1920年代アメリカの歯科医師によってハリウッド映画の撮影用に考案されました。この時期、歯の外観を改善するための方法として、ポーセレンを用いた技術が模索されました。
1980年代になり、薄くて強度のあるセラミック材料や接着材料の進歩により、ポーセレンラミネートべニアが再評価され、特に審美歯科の分野で積極的に取り入れられ、より自然な外観と耐久性が実現しました。
1990年代以降、CAD/CAM技術の導入により、個々の患者に合わせた高精度のラミネートべニアが製作可能となりました。また、さらなる接着技術の向上により、ラミネートべニアの成功率も向上しました。
現在では、ジルコニアの材料開発がさらに進み、強度だけではなく見た目の改善、特に透明感の向上は素晴らしくラミネートべニアは、前歯の審美的な改善と同時に、機能的な治療にも広く応用されています。
さまざまな色や形状の選択肢があり、個々の患者さんのニーズに応じた治療が可能です。
ラミネートべニアの利点・欠点について
ラミネートべニア(porcelain laminate veneer)の利点と欠点について説明いたします。
利点
| 見た目の改善 | 自然な歯の色や形に合わせて製作できるため、見た目の改善に優れています。 |
| 最小限の侵襲 | 歯の削る量を最小限に抑えることができます。 |
| 耐久性 | ポーセレンは非常に硬く、摩耗や変色に耐性があります。 |
| 汚れにくい | セラミックの表面は滑らかで、プラークや着色が付きにくいため、口腔衛生を保ちやすいです。 |
| 清掃性の向上 | セラミックシェルの表面性状や形態の回復により口腔内の清掃効果が高まり、2次う蝕や歯周病を抑制できます。 |
| 機能の回復 | かみ合わせの改善や歯の並びの改善を通じて、咬む力を回復することができます。 |
欠点
| コスト | 自由診療で高額(大体1本5万円~20万円)になることが多く、基本、保険が適用されません。 |
| 破損の可能性 | 強い衝撃や不適切な咬合によって、ラミネートが破損・脱離する可能性があります。 |
| 適応症の制限 | かみ合わせの問題、大きな歯の欠損や中等度や重度の歯周病がある場合には、適用できないことがあります。 |
| 接着の問題 | 接着技術に依存するため、接着操作や接着材料に不備があると脱離する。 |
ラミネートべニアの特徴について
以下のような特徴があります。
特徴
| 厚み | ラミネートべニアは非常に薄く、通常は0.5mm~1.0mm程度の厚さです。これにより、歯を大きく削ることなく装着できます。 |
| 素材 | セラミック(ポーセレンもしくはジルコニア)を使用しており、極めて自然な歯の色や形態に仕上がります。 |
| 耐久性 | セラミックは強度が高く、摩耗や変色に対する耐性があります。適切なケアを行えば、長期間にわたって使用可能です。 |
| 見た目 | 光を透過し、自然な歯のような透明感を持つため、非常に美しい仕上がりが得られます。また、色や形を個々の患者に合わせてカスタマイズできます。 |
| 接着技術 | 高度な接着技術・材料を用いることで、ラミネートべニアが歯にしっかりと固定されます。これにより、外部からの影響を受けにくくなります。 |
| 適応範囲 | 歯の変色、軽度の欠損、形状の不整、咬合不全など、さまざまな見た目の問題に対応可能です。 |
| 最小限の侵襲 | 基本的にエナメル質内に限局されるため、歯を削る量が極端に少なくなります。そのため虫歯になりにくく歯の健康を保ちながら審美的な改善が図れます。 日本人の唇側歯頚部エナメル質の厚みは、0.3mm程度の場合も多く、切削の際はエナメル質がなくならないように象牙質が露出しないように慎重に削る必要があります。 |
| メンテナンス | 特別なメンテナンスは不要ですが、通常通り、当該歯を含めたお口の中の定期的な検診や適切な口腔衛生が推奨されます。 |
ラミネートべニアの適応症・禁忌症
ラミネートべニアの適応症と禁忌症について詳しく説明します。
適応症
ラミネートべニアは、以下のような症状や状態に対して適用されます。
| 歯の変色 | 内因性または外因性の変色があり、ホワイトニングでは改善しない場合。 |
| 軽度の歯の欠けや摩耗 | 軽度の欠けや摩耗がある歯を修復するため。 |
| 歯の形状不良 | 不揃いな形状やサイズの歯を整えるため。 |
| 隙間のある歯並び | 歯と歯の間に隙間がある場合、ラミネートべニアで整えることができます。 |
| 咬合の改善 | 咬合のバランスを整えるための補助的な手段として。 |
| 審美的な改善 | 美しい笑顔を実現するための見た目の改善が目的。 強い変色により、人前で笑えない、写真が取れない等の心理的負担を解消できます。 |
禁忌症
ラミネートべニアが適用できない場合や慎重に行うべき状態は以下の通りです。
| 中等度・重度の歯周病 | 歯周病が進行している場合、治療が必要です。 |
| 重度の虫歯 | 虫歯が深刻な場合は、まず虫歯治療が優先されます。 虫歯の範囲によっては適応ができません。 |
| 不適切な咬合 | 咬合が不適切で、強い力がかかる場合は、ラミネートべニアが脱離・破損するリスクがあります。 |
| 歯の強い摩耗や欠損 | 歯が大きく欠けている場合や、根の状態が悪い場合は、ラミネートべニアが適用できません。 |
| 不適切な口腔衛生 | 十分な口腔衛生が保たれていない場合、2次う蝕やセメント崩壊によりラミネートべニアの寿命が短くなる可能性があります。 |
| アレルギー | 使用される材料に対するアレルギーがある場合は、事前に相談が必要です。 |
ポーセレンラミネートべニアの特徴
ラミネートべニアの特徴について詳しく説明します。
ポーセレンラミネートべニアの特徴
| 薄さ | ポーセレンラミネートべニアは非常に薄く、通常0.5mmから1.0mm程度の厚さです。これにより、歯を大きく削ることなく装着できます。 |
| 素材 | 高品質なセラミック(ポーセレンもしくはジルコニア)を使用する場合、自然な歯の色や質感に近い仕上がりが可能です。 |
| 見た目の特性 | 光を透過し、自然な歯のような透明感を持たせることができるため、非常に美しい仕上がりが得られます。色や形を個々の患者に合わせてカスタマイズできます。 |
| 耐久性 | ポーセレンは強度が高く、摩耗や変色に対する耐性があります。適切なケアを行えば、長期間にわたって使用可能です。 |
| 接着技術 | 高度な接着技術を用いることで、ラミネートべニアが歯にしっかりと固定され、外部からの影響を受けにくくなります。 |
| 最小限の侵襲 | 歯を削る量が少ないため(約0~1.0mm)、歯の健康を保ちながら審美的な改善が図れます。 |
| 適応範囲 | 歯の変色、軽度の欠け、形状の不整、咬合不全など、さまざまな審美的問題に対応可能です。 |
| メンテナンス | 特別なメンテナンスは必要なく、通常の歯磨きや定期的な歯科検診で十分です。 |
合着後の調整ポイント
| 咬合の確認 | 合着後、上下の歯との咬合を確認します。特に、咬合接触が均等かどうかをチェックし、必要に応じて調整します。 |
| 形状の調整 | べニアの形状が自然な歯の形に合っているかを確認します。形が不自然な場合は、研磨や修正を行います。 |
| 色調の最終確認 | べニアの色が周囲の歯と調和しているかを再確認します。必要に応じて、色調の調整を検討します。 |
| 表面の滑らかさ | べニアの表面が滑らかであることを確認します。粗さや不均一がある場合は、研磨を行います。 |
| 接着剤の除去 | 大なり小なり必ず余剰のセメントが残存しております。拡大鏡を見ながら合着後に接着剤がはみ出している場合、慎重に除去します。接着剤の取り残しがあれば除去します。これにより、見た目が改善され、口腔内の清潔さも保たれます。 |
| 患者へのフィードバック | 患者に咬合や形状についての感触を確認し、満足度を得ることが重要です。患者の意見を反映させることで、最終的な仕上がりが向上します。 |
| 定期的なフォローアップ | 合着後、定期的なフォローアップを行い、べニアの状態や口腔内の健康状態を確認します。 |
| メンテナンスの指導 | 患者に対して、べニアのメンテナンス方法や注意点を説明し、長持ちさせるためのアドバイスを行います。 |
ラミネートべニアのシェードテイキング
ラミネートべニアのシェードテイキング(シェードマッチング)について、以下に詳細をまとめます。
シェードテイキングの重要性
シェードテイキングは、ラミネートべニアを製作する際に、自然な歯と調和する色合いを選定するプロセスです。
これにより、見た目が自然で美しい仕上がりが得られます。
また、自然かどうかは、術者サイドの考えであり、歯の色にコンプレックスに持っていた人が望む白さについて十分注意して選択する必要があります。
シェードテイキングの手順
1. 照明条件の設定
自然光に近い環境でシェードを確認することが重要です。
異なる照明下では色の見え方が変わるため、適切な照明を使用します。
2. シェードガイドの使用
シェードガイド(色見本)を使用して、患者の歯の色と比較します。
シェードガイドには、様々な色調が含まれているため、最も近い色を選びます。
3. 歯の状態の確認
患者の歯の色だけでなく、歯の透明感や色ムラも考慮します。
これにより、より自然な色合いを選定できます。
4. 患者さんの意見を尊重
患者にシェードを確認してもらい、希望の色合いについてフィードバックを得ます。
患者の好みを反映させることが重要です。
特に前歯部全体の強い変色の改善を求めてくる患者さんについては、術者が自然と思われる白さでは患者さんが納得しない場合が多いので、どこまで白くするかは、患者さん主体で決定する必要があります。
5. シェードの記録
選定したシェードを記録し、技工士に正確に伝えるための情報を提供します。
6. 試適の実施
最終的なシェードが決定したら、試適を行い、実際に患者の口腔内での見え方を確認します。
必要に応じて微調整を行います。
注意点
時間の確保
シェードテイキングには時間がかかる場合があるため、十分な時間を確保して行います。