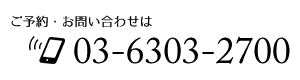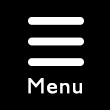🦷歯科における多職種連携の重要性 ― 全身の健康と地域包括ケアを支えるために
【1】なぜ歯科に多職種連携が必要なのか?
◉ 背景と課題
- 日本は超高齢社会に突入し、要介護高齢者が急増していること
- 口腔の問題(咀嚼・嚥下・構音障害など)は、栄養不良、誤嚥性肺炎、社会的孤立といった多面的リスクと直結していること
- 歯科単独での対応には限界があり、医科・介護・リハビリとの連携が不可欠であること
【2】多職種連携の目的
| 目的 | 内容 |
| 全身的健康の維持 | 栄養状態、感染症予防、サルコペニア・フレイル予防 |
| QOLの向上 | 食事・会話・社会参加の支援 |
| 介護予防・重度化防止 | オーラルフレイルや誤嚥予防 |
| 地域包括ケア | 住み慣れた地域で自立した生活を継続できる体制づくり |
【3】歯科と関わる主な職種と連携内容
| 連携職種 | 歯科との主な連携内容 |
| 医師(主治医) | 全身状態の共有(糖尿病、心疾患、服薬) 抗血栓薬管理、感染症リスク |
| 看護師・訪問看護師 | 口腔ケアの実施支援、誤嚥の兆候観察 |
| 管理栄養士 | 咀嚼・嚥下に応じた食事設計、栄養状態の評価 |
| 言語聴覚士(ST) | 嚥下・構音評価、リハビリ指導 |
| 介護職員・ヘルパー | 口腔清掃支援、義歯の管理、食事介助との連携 |
| 薬剤師 | 口腔乾燥・副作用の相談、服薬管理支援 |
| ケアマネジャー | 歯科訪問・通院の調整、計画書への反映 |
| 作業療法士・理学療法士 | 食事姿勢の指導、ADL向上支援 |
【4】歯科医療従事者に求められる役割
● 歯科医師:
- 医療連携におけるハブ的存在
- 診断と治療、機能評価、情報提供
- 多職種カンファレンスへの参加と意見発信
● 歯科衛生士:
- 専門的口腔ケア(POHC)の提供
- 他職種への口腔ケア技術の指導・助言
- 在宅・施設での口腔衛生管理の橋渡し
【5】歯科における多職種連携の実例
◆ 例1:誤嚥性肺炎予防
- 歯科医師が口腔診査と嚥下評価
- 言語聴覚士が嚥下訓練を指導
- 看護師・介護職が口腔ケアを継続
- → 誤嚥性肺炎の発症率が大幅に減少
◆ 例2:栄養改善とフレイル予防
- 管理栄養士が食事内容を提案
- 歯科医師が義歯調整で咀嚼力回復
- 介護職が食事介助時の配慮
- → 体重増加、ADL改善、生活意欲向上
【6】多職種連携のポイントと課題
◉ 成功のためのポイント
- 共通目標の設定:「患者のQOL向上」「誤嚥予防」など
- 情報共有の仕組み:ICT活用、記録の共有、口頭連絡
- 相互理解と尊重:職種ごとの専門性・役割の理解
- 定期的なカンファレンス参加:情報のアップデートと連携強化
◉ 主な課題
- 診療報酬制度の制限(特に外来歯科での連携は評価されにくい)
- 時間・人員不足
- 情報共有ツールの整備不足
- 職種間の役割の境界や認識のズレ
【7】歯科からのアプローチ強化策
- 訪問歯科診療の活用:施設・在宅での支援体制構築
- 研修・教育活動:他職種対象の口腔ケアセミナー開催
- 行政・地域との連携:地域包括支援センター、在宅医療支援診療所との協働
- 診療所内での多職種配置:STや栄養士、看護師とのチーム医療実現
【8】まとめ:歯科の力を地域医療へ
「口からはじまる健康づくり」を実現するために、
歯科は 予防・回復・支援のプロフェッショナルとして、
多職種連携の中核的な存在になることが求められています。
歯科からの積極的な関与が、
高齢者の 生活の質(QOL)、そして 生存率の向上につながります。