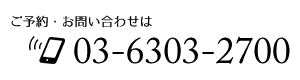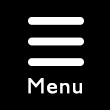● 咬合、下顎運動関連の基礎知識を説明いたします。
・歯列: 口腔内を(咬合面)方向から見ると列をなしている
・歯列弓:歯の列を臼歯では(頬側)咬頭頂または中心溝、犬歯では尖頭、切歯では切縁を連続して見ると弓状を示す
・前後的咬合彎曲: (上顎)歯列を咬合平面の高さで(側方)から観察した時、頬側咬頭頂を連ねて得られる曲線
・スピーの彎曲 :(下顎)歯列を(側方)から観察した時、小臼歯および大臼歯の頬側咬頭頂を連ねる曲線
・モンソン球面説: 下顎の歯牙は直径8インチ(半径4インチ)の球面に接する。そしてこの中心は篩骨の鶏冠にある。
・モンソンカーブ :モンソン球面説に導かれる咬合彎曲で半径4インチの下方に凸の球面をなすカーブ。
・側方咬合彎曲(ウイルソンカーブ): 上下歯列を前方から観察した時、下顎の下方に凸な咬合彎曲。下顎歯は舌側に傾斜しているため下方に凸の彎曲でありスピーの彎曲とともに下顎の側 方運動時の適度な歯の接触を生み機能向上に役立つ。 左右臼歯の頬舌側咬頭頂を連ねる曲線
・咬合平面 :(下顎)中切歯切縁および左右(下顎)第二大臼歯遠心頬側咬頭頂を含む平面
・フランクフルト平面: 左右の眼点(眼窩下縁)と耳点(耳珠上縁)を含む平面 再現性の高い水平基準面であるため各種咬合器の上顎模型付着のための基準平面
・カンペル平面: (鼻翼)下縁と耳珠上縁(外耳道下縁)を結ぶ線 フランクフルト平面に対して約15°前傾 咬合平面に対して平行であることから別名、補綴学的平面ともよばれる
・咀嚼: 食物を口腔内に取り入れ切断、破砕しながら唾液と混和し嚥下が可能となるまでに食塊を形成する一連の動作 ・嚥下 咀嚼によって形成された食塊が、口腔から咽頭、食道を経て胃に送り込まれる一連の無意識的、反射的な消化運動
・ 中心位:関節窩内で緊張することなく、両側の下顎頭が最前上方に位置した時の上顎に 対する下顎の位置関係。
・ターミナルヒンジポジション(終末蝶番位)。 (1)中心位は歯の存在とは無関係に成立する。 (2)咬合の不安定な場合でも、咬頭嵌合位が消失されているような症例でも計測可能。 (3)筋活動の影響を受けにくい。
・ 中心咬合位:対合する咬合面が最大の接触関係をもたらす時の下顎の位置。
(1)歯によって決定される位置。
(2)顎口腔系に異常のない正常有歯顎者では、中心咬合位≒筋肉位 中心咬合位とイコールではないが近い位置としてやや下方へ近い方から発音位についで嚥下位となる
・咬頭嵌合位:上下の歯列が咬頭対窩の関係で嵌合した状態にあるときの下顎の位置 咬頭嵌合位≒中心咬合位
・下顎安静位: 下顎は一連の下顎運動が終了したあとに上顎との間でほぼ一定の距離を保って静止し、再びその位置から運動を始める。このような下顎の静止位をいう。
補綴学的基準となる下顎位で、生涯を通じて比較的恒常性が高いことから無歯顎者に対する全部床義歯の咬合高径を決定する1つとして用いられる。
・ボンウィルの三角: 左右の下顎頭の上面中央と下顎前歯切端中央を結ぶと一辺が4インチ(約10cm)の正三角形になる。平均値咬合器はこの考えを取り入れて作られた。
・バルクウィル角: 両側下顎頭を結んだ線の中央と切歯点とを結んだ仮想線が咬合平面となす角で平均26°。 これも平均値咬合器の設計の基準となっている。
・偏心位: 中心咬合位または中心位から、下顎を水平的に移動させた時の下顎の位置 前方位、側方位、後方位
・作業側: 下顎を外側方に動かした時の移動側
・平衡側(非作業側): 作業側の反対側 ・ベネット角(側方顆路角) 側方運動時に平衡側の下顎頭の運動路が、水平面で正中矢状平面となす角度 内方への入り方の程度 有歯顎者で約15°
・ ベネット運動: 作業側顆頭の外側方への移動 平均約1㎜ ・ ゴシックアーチ 側方切歯路について描記装置を用い左右の側方限界運動によって水平基準面上に描くことができる矢じり状の図形
・ フィッシャー角: 矢状面の運動経路である矢状顆路について前方運動時と側方運動時では異なった傾斜を示す。この傾斜の差をいい平均5°といわれる。
・サイドシフト: 側方運動時に起こる下顎全体の移動のこと
・イミディエートサイドシフト: 平衡側顆頭が、側方運動時初期に内側方向へ移動する現象 これは、咬頭嵌合位付近の咬合面形態に影響を及ぼすといわれる
・プログレッシブサイドシフト: ごく初期に一時内側方向にずれるイミディエートサイドシフトに続く前下方への移動する現象
・蝶番運動軸(ヒンジアキシス): 模型の咬合器付着の基準点
・下顎運動: 上顎に対する下顎骨全体の運動 下顎は一定の範囲で自由に動くことができる反面、顎関節の構造や咀嚼筋の規制を受けその運動範囲は限られる。下顎運動に関与する主な筋は、咀嚼 筋(咬筋、側頭筋、内側翼突 筋、外側翼突筋)や顎舌上筋群(顎二腹筋)
・{下顎運動に伴う筋肉の動きのまとめ}
・閉口運動~咬筋、側頭筋、内側翼突筋 ・開口運動~外側翼突筋、顎ニ腹筋、顎舌骨筋、オトガイ舌骨筋 ・前方運動~外側翼突筋(咬筋浅部、内側翼突筋、開口筋群) ・後方運動~側頭筋後部筋束(咬筋、内側翼突筋、舌骨上筋群)
・側方運動(左側方運動の場合)~右外側翼突筋、左側頭筋後部筋束(左閉口筋、右顎舌 骨筋)
●{下顎位、下顎運動関連のポイント整理}
・作業側顆頭がわずかに外側方に移動する➡ ベネット運動 ・矢状顆路角~矢状顆路が水平基準面となす角度。
・ベネット角(側方顆路角)~側方運動の際に平衡側の下顎頭の示す運動路が水平面で正中矢状平面となす角度。0~30°、平均7°。
・矢状切歯路角~矢状切歯路が矢状面において水平基準面となす角度。
・側方切歯路角~側方切歯路を(水平)面に投影した時の左右の切歯路がなす角度。 一般にゴッシックアーチ展開角として知られ、通常、100~140度の範囲に分布。
・側方運動時作業側顆頭は外方へ小さく移動回転する。
・筋電図で測定できるのは、咀嚼周期と下顎安静位である。
・外側翼突筋の基本的な機能は関節円板と顆頭を前方に移動させる。
・右側運動時、平衡側顆頭は大きく移動し、関節結節のほぼ直下まで移動する。
・BULLの法則は、作業側の咬合調整に利用する。
・矢状顆路角、側方顆路角は、平衡側で生じるものをいう。
・右側運動時作業側顆頭の前方移動防止をしているのは作業側側頭筋の後部筋束。
・側頭筋の前部筋束は、挙上筋、閉口相のみで活躍、しかし、後部筋束は、挙上作用はなく、下顎を後引か位置決定に作用する。また中部筋束は、前 方運動時活躍する。
・顎関節 下顎骨と側頭骨下顎窩との間で頭蓋と下顎を連結しているもので、頭蓋にある唯一の関節。その特徴は、左右で一対の関節を形成する複関節であり、 一側の運動が他側へも影響を及ぼす。下顎運動時の下顎頭の運動様式は、回転、滑走、および両者の複合運動である。
●ポッセルトのバナナ
咀嚼のための下顎運動の多くは咬頭嵌合位―開口―作業側への偏位―閉口―上下の接触滑走―咬頭嵌合位 ル)咀嚼運動はこれの繰り返し。
咀嚼サイクル(チューイングサイク 実際、顎の動かし方を考えてみると機械のような運動ではなくもっと自由に動かすことができる気がする、実はかなり制約されているのだ。
下顎切歯の切端部分P点は一定の定まった範囲から外に出ることができないし、どの個人も似たような形をしている。それは、下顎を頭蓋につなぎとめている筋や靭帯があるからである。この眼に見えない籠の形を描いて見せたのがポッセルトである。
下顎切歯の切端部分の動ける範囲はバナナ形を呈する。
このバナナ形をした経路図を正中で切って横から見たものがあの有名な図で {ポッセルトの図形}
1:中心位(後方歯牙接触位)
2:中心咬合位(咬頭嵌合位)
5:最大前方位(前方咬合位)
r:下顎安静位
Ⅲ:最大開口位 2~5
:前方滑走運動路 2~1
:後方運動滑走路 上記2つの運動路は上下顎の歯牙により誘導される運動である。
5~Ⅲ:前方限界運道路
1~Ⅱ~Ⅲ:後方限界運動路
H(1~Ⅱ):終末蝶番運動路 上記、3つの運動路は開、閉口運動で歯牙による影響を受けない。