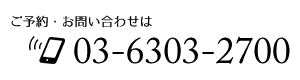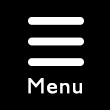●被せ物を最終的につける前までのチェック、調整について詳しく説明いたします。
クラウン試適、調整の順序
1 隣接歯間関係の確認・調整
2 適合状態の確認・調整
3 咬合の確認・調整(中心咬合位→側方位→前方位)
1 隣在歯間関係 ・隣在歯の歯間関係を検査する方法~コンタクトゲージ、デンタルフロス、咬合紙、サンドブラ スト処理 ・該当クラウン以外の部分と同じような状態に調整するのが基本
・機能的なコンタクトの強さは臼歯部で平均上顎90μm,下顎70μmである。
・コンタクトの臨床的基準はおおよそ50μmのコンタクトゲージが入り110μmのコンタクトゲージが入らない状態である。
・110μm が入って150μmが入らない場合は不可ではなく注意。
・咬合紙は35μm程度のものを使用
・咬合紙を引き抜いて破れるようだと厳密すぎ(やや抵抗を持って引き抜けるくらいがよい)
・ [鼓形空隙と食片圧入との関係] 上部鼓形空隙は垂直的な食片圧入に最も関係する。⇒上部鼓形空隙が上方に広い場合や失われている場合また 辺縁隆線が不一致な場合も食変圧入が起こりやすい。
頬舌的鼓形空隙においてコンタクト部が極端な点状をとり頬舌的鼓形空隙が広すぎる場合⇒圧入した食片の脱 出は容易であるが,食物が過度に歯間歯肉を刺激し,不安定となる
・ 下部的鼓形空隙は正常な歯周組織において歯間歯肉で閉塞されている。
・ 下部的鼓形空隙において広すぎる場合,食片圧入が起こりやすく不快感も増すため,最小の歯間ブラシが入る 程度でできるだけ狭くする方が望ましい。
2 適合状態の確認 視診、探針、ホワイトシリコーンでの確認
3 咬合関係
・ 咬合関係の診査
(1) 視診
(2) 触診
(3) 患者の感覚
(4) 引き抜き試験:咬合紙,オクルーザルレジストレーションストリップス
(5) 咬合接触像:シリコーン・チェックバイト法,咬合紙,オクルーザルインディケーティングワックス
(6) 咬合紙などによる印記法:各種咬合診査器,咬合音診査器
☆咬合接触検査の方法
1) ワックスによる方法
2)咬合紙法
3)シリコーンゴム検査材による方法(シリコーン・チェックバイト法)
4)感圧フィルムによる方法
5)引き抜き試験
・咬合紙法~約30μmの厚さの咬合紙
・シリコーン・チェックバイト法~咬合記録をライトボックス上に置き、光の透過状態から咬合接触の緊密度を 観察する。
・感圧フィルムによる方法~T-スキャンⅢは、咬合接触位置、咬合接触力、咬合接触時間をチェアサイドで記録 できる。センサーシートを上下顎歯列間に介在して、接触圧の大きさを電気抵抗値 から検出する。早期接触の有無、ガイドの様式、咬頭干渉の有無を検査。
・引き抜き試験~上下顎各歯での咬合接触の強さを検査する方法。咬合紙やストリップス(シムストック)を用いる。
・最終的に研磨面の形態修正、研磨を行う。
・被せ物の内面を材料の性質に応じた適正な内面処理を行う。
サンドブラスト処理+プライマー処理