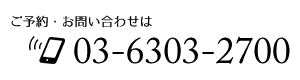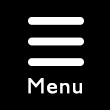クラウン(被せ物)にはどのような種類があるでしょうか。
詳しく解説していきます。
クラウンは、大きく分けて3つに分けられます。
Ⅰ 全部被覆冠
歯の頭の部分全体を覆う被せ物です。
構造的に堅固で保持する力が強くより外れにくい構造となります。
また自由な形や色を付けられます。
歯を削る量が多く生体への侵襲が大きい。
① 全部金属冠
② 陶材焼付冠
③ レジン前装冠
④ オールセラミッククラウン
Ⅱ 部分被覆冠
歯冠の一部を被覆するクラウンで、歯質の削除量が少ないため、歯髄を損傷するリスクは少ないが、全部被覆冠と比べ支台装置としての保持欲が少ない。また、フィニッシュラインの全長距離が長いため、2次う蝕になりやすい。このため、口腔清掃状態が悪いもしくはう蝕活動性が高い患者さんには適応できない。
1 3/4クラウン、4/5クラウン
2 ピンレッジ
3 プロキシマルハーフクラウン
4 アンレー
5 7/8クラウン
6 ラミネートべニア
7 接着ブリッジの支台装置
Ⅲ 継続歯
歯冠部とポスト部が一体となった支台装置でポストクラウンとも呼ばれる。
歯肉縁に沿った支台歯形態を付与する。
●全部被覆冠の種類と特徴
1 陶材焼付冠
2 レジン前装冠
3 オールセラミッククラウン
4 ハイブリッド型コンポジットレジンクラウン
5 CAD/CAMクラウン
6 全部金属冠
1 陶材焼付冠
① ディギャッシング→1050℃真空中
② 光の透過性がある
③ 審美性に優れる
④ 耐摩耗性に優れる
⑤ 支台歯、セメントの色調に影響を受ける
⑥ 歯質切削量は全部金属冠より多い
⑦ 衝撃に弱い
⑧ クリアランス不足の場合破折しやすい
⑨ 製作は複雑
⑩ 製作コストが高い
・適応症→審美性が要求される部位の歯冠修復及びブリッジの支台装置
・禁忌症→歯髄腔の大きな生活歯、著しく咬合力の強い患者、ブラキシズム症例 若年
者
2 レジン前装冠★ 陶材焼付冠に準じる。製作法は異なる。
ハイブリッド型コンポジットレジンの場合、適応禁忌メタルデザイン等ほぼ陶材焼付冠に準じる。
陶材焼付冠と適応症で異なること
① コーヌステレスコープ外冠の前装部
② ロングスパンブリッジの前装部
従来型前装用コンポジットレジンで前装する場合、陶材焼付冠とメタルコーピングのデザインが異なる。 直接力がかかる所はメタルにする。
前装用コンポジットレジンは可及的に無機質フィラーの配合を多くした。→機械的強さの向上 ・ 結合様式 機械的維持装置→リテンションビーズ(粒径0.2mm) アルミナサンドブラスト処理 接着→金属接着プライマー(硫黄や酸性の官能基)
製作法
1 メタルコーピングの前処理 2 前装用レジンの築盛 3 前装用レジンの重合 4 仕上げ・研磨
2 メタルコーピングの前処理 前装面辺縁部にあるリテンションビーズを除去する。 2 前装用レジンの築盛 オペークレジンの塗布 何層かに分けて硬化させる デンティン色ペーストの築盛(色調、形態の基本) エナメル色ペーストの築盛(透明感、立体感を表現)
3 前装用レジンの重合 基本は光線照射
4 仕上げ・研磨(陶材に準じる) 荒研磨~ダイアモンドポイント、カーバイドバー、カーボランダムポイント 20 中研磨~シリコーン 仕上げ研磨~リュージュ、ダイアモンドを含むペースト、ホイール
3 オールセラミッククラウン
最大の特徴⇒天然歯と同様の色調をもち歯周組織に調和した修復が行えること
陶材焼付冠との違い⇒光の透過性があり、アレルギー反応なし
☆【オールセラミッククラウンの重要ポイント】
① 歯肉着色が生じない
② 光の透過性がある
③ 支台歯、セメントの色調に影響を受ける
④ 審美性に優れる
⑤ 耐摩耗性に優れる
⑥ 歯質切削量は陶材焼付金属冠より多い
⑦ 衝撃に弱い
⑧ クリアランス不足の場合破折しやすい
⑨ 製作は複雑
【適応症】
① 全部被覆冠の適応症で特に高度な審美性が必要な症例
② 単冠あるいは少数歯のブリッジ(前臼歯3歯ブリッジ)
【禁忌症】
① 多数歯欠損・多数歯支台のブリッジ症例
② ブラキシズムやクレンチング症例
③ 歯冠長が短い症例
④ 生活歯で歯髄が露出する可能性のある症例
金属に迫る強度や破壊靭性をもつジルコニアの登場によりオールセラミックブリッジは前、臼歯部に応用できるようになった。ジルコニアを切削後、半焼結のコーピングを1300℃以上の高温で完全に焼結させると高強度ジルコニアコーピングができる。ジルコニアは焼結の段階で20%以上収縮するのであらかじめCADにより収縮の補正が行われている。ジルコニアコーピング上に歯冠色陶材を築盛あるいはプレス成型してクラウンブリッジが完成する。
➡近年,歯冠色をもつ半透明ジルコニアが開発され,歯冠色陶材を積層しないでジルコニア単体でクラウンやブリッジが製作できるようになった。
・利点➡破折しにくく大臼歯の補綴に有効。
・欠点➡対合歯を咬耗させやすい(咬合調整後の研磨が重要)☚
4 ハイブリッド型コンポジットレジンクラウン
特にCAD/CAMによるハイブリッド型コンポジットレジンクラウン
ハイブリッド型コンポジットレジンはメタルフリー修復に広く応用
金属アレルギー対策
フィラー含有率が70%~90%(粒子サイズの異なるフィラーを組み合わせた)
【適応症】
① 審美性の要求される部位の歯冠修復
前歯の切縁や臼歯咬合面も被覆可能
② 審美性の要求されるブリッジの支台装置やポンティック
③ 審美性の要求されるインプラント上部構造
④ コーヌステレスコープ外冠の前装部
1CAD/CAMクラウンでの製作
2従来型の製作法は
ジャケットクラウンの場合
1 通法通り作業模型作製
2 歯型にスペーサー塗布
3 オペークレジン築盛、光重合
4 デンティン色、エナメル色ペースト築盛、仮重合
5 咬合、形態修正後最終重合(光重合+加熱重合)
6 調整、研磨
5 CAD/CAMクラウン
使用される材料~ジルコニア,セラミック,コンポジットレジン,チタン,コバルトクロム
【ジルコニアの特徴】
① 生体親和性が高い
② 高強度
③ 複製が可能
④ エックス線不透過性
⑤ 吸水性なし
⑥ CAD/CAMにより製作
⑦ ジルコニア自体では詳細な色調回復ができない。
⑧ 鋳造による欠陥や変形がなく安定した物性が得られる
⑨ フレームと築盛した陶材との結合が強固でない可能性がある
⑩ 完全焼結の段階で20%以上収縮するので半焼結体の段階で20%以上大きく加工する
(金属の場合1.5~2.5%程度の鋳造収縮)
⑪ 半焼結のブロックを切削し、切削後に半焼結のジルコニアを1300℃以上で完全に焼結する
☆CAD/CAM法によるオールセラミッククラウン,ハイブリッドコンポジットレジンクラウンの製作上の注意点
➡★特に支台歯形成,咬合調整,装着が重要☚これ最重要
オールセラミッククラウンの形成に準じるが,
1)形成面を滑沢にしてアンダーカットを作らない
2)隅角部を曲面に仕上げ鋭利な部分を残さない。
3)フィニッシュラインから軸面にかけて曲面で移行するラウンデッドショルダーかディープシャンファー形態とする。
4)クラウンの厚みが均一になるようにする。
ジルコニア、ハイブリッドコンポジットレジンは通報通り試適調整し,接着性レジンセメントを用いて合着する。その際,コンポジットレジンクラウンやセラミッククラウンは,サンドブラスト処理、シラン処理後接着性レジンセメントを用い装着する。非シリカ含有のジルコニアやアルミナはリン酸エステル系モノマー(MDP)で処理する。
CAD/CAM法によるクラウンの製作過程
1 間接法➡作業模型製作(通法通り支台歯形成、印象採得を行う。対合歯模型とインターオクルーザルレコードも必要)
① スキャン・光学印象(歯型、対合歯模型、インターオクルーザルレコード)
② CAD・設計
③ CAM・削り出し(ジルコニアクラウン型、ジルコニアコーピング型ともに半焼結のブロックを切削。切削後半焼結のジルコニアを1300℃以上の高温で完全焼結する)
④ クラウン完成(クラウン型はこれで完成。ジルコニアコーピングの場合、陶材を築盛、焼成して完成)
2 直接法➡支台歯や対合歯を口腔内カメラでスキャン
① 口腔内スキャン。光学印象(支台歯、対合歯をスキャン。頬側からスキャンして咬合採得する)
② CAD・設計
③ CAM・削り出し(ジルコニアクラウン型、ジルコニアコーピング型ともに半焼結のブロックを切削。切削後、半焼結のジルコニアを1300℃以上の高温で完全焼結する)
④ クラウン完成(クラウン型はこれで完成。コーピング型の場合、樹脂製模型上にて、ミリングから得たジルコニアコーピングに陶材を築盛、焼成して完成)
ハイブリッドコンポジットレジンクラウンの場合、ミリングから得られたクラウン原型を研磨して完成
陶材を築盛するオールセラミッククラウンの場合、3Dプリンターで樹脂製の模型を製作する。
CAD/CAM直接法最大のメリットは印象材を用いた印象採得や咬合採得材料を用いた咬合採得を行わなくてよいこと
6 全部金属冠
歯冠全体を被覆する金属製のクラウンで、金合金、金銀パラジウム合金、純チタンなどの金属を用いる。
Ⅱ 部分被覆冠
部分被覆冠の1つであるラミネートべニアについてご説明いたします。
ラミネートべニア法は見た目の優れた治し方で、歯の表面を一層削って白い透明性の高いセラミックもしくはレジンシェルを歯に貼り付ける方法です。
ではどのくらい歯を削るかというと、0~1.0mm程度で、一切歯を削らないこともあります。
主に審美的な改善を目的として使用される薄いセラミックもしくはハイブリッド型コンポジットレジン製のシェルを接着性レジンセメントで装着する方法です。
薄くて美しい仕上がりが特徴で、審美的な改善に非常に効果的な治療法です。個々の患者のニーズに応じたカスタマイズが可能であり、歯をあまり削ることなく自然な外観を実現できます。
ラミネートべニアは、審美歯科の進化とともに発展してきた技術であり、現在も多くの患者に利用されています。
ジルコニアをはじめとする各種セラミック材料の進歩および接着材料や技術の進歩により、より自然で耐久性のある治療法としての地位を確立しています。
ラミネートべニアは多くの審美的な問題に対して有効ですが、適応症と禁忌症を理解し、適切な診査が行われることが大切です。
【歴史の概要】
ラミネートベニアの起源は1920年代アメリカの歯科医師によってハリウッド映画の撮影用に考案されました。この時期、歯の外観を改善するための方法として、ポーセレンを用いた技術が模索されました。
1980年代になり、薄くて強度のあるセラミック材料や接着材料の進歩により、ポーセレンラミネートべニアが再評価され、特に審美歯科の分野で積極的に取り入れられ、より自然な外観と耐久性が実現しました。
1990年代以降、CAD/CAM技術の導入により、個々の患者に合わせた高精度のラミネートべニアが製作可能となりました。また、さらなる接着技術の向上により、ラミネートべニアの成功率も向上しました。
現在では、ジルコニアの材料開発がさらに進み、強度だけではなく見た目の改善、特に透明感の向上は素晴らしくラミネートべニアは、前歯の審美的な改善と同時に、機能的な治療にも広く応用されています。さまざまな色や形状の選択肢があり、個々の患者さんのニーズに応じた治療が可能です。
ポーセレンラミネートべニア(porcelain laminate veneer)の利点と欠点について説明いたします。
【利点】
見た目の改善:自然な歯の色や形に合わせて製作できるため、見た目の改善に優れています。
最小限の侵襲:歯の削る量を最小限に抑えることができます。
耐久性:ポーセレンは非常に硬く、摩耗や変色に耐性があります。
汚れにくい:セラミックの表面は滑らかで、プラークや着色が付きにくいため、口腔衛生を保ちやすいです。
清掃性の向上:セラミックシェルの表面性状や形態の回復により口腔内の清掃効果が高まり、2次う蝕や歯周病を抑制できます。
機能の回復:かみ合わせの改善や歯の並びの改善を通じて、咬む力を回復することができます。
【欠点)】
コスト:自由診療で高額になることが多く、基本、保険が適用されません。
破損の可能性:強い衝撃や不適切な咬合によって、ラミネートが破損・脱離する可能性があります。
・適応症の制限:かみ合わせの問題、大きな歯の欠損や中等度や重度の歯周病がある場合には、適用できないことがあります。
・接着の問題:接着技術に依存するため、接着操作や接着材料に不備があると脱離す
【ラミネートべニアの特徴に】ついて
【特徴】
- 厚み:
• ラミネートべニアは非常に薄く、通常は0.5mm~1.0mm程度の厚さです。これにより、歯を大きく削ることなく装着できます。 - 素材:
• セラミック(ポーセレンもしくはジルコニア)を使用しており、極めて自然な歯の色や形態に仕上がります。 - 耐久性:
• セラミックは強度が高く、摩耗や変色に対する耐性があります。適切なケアを行えば、長期間にわたって使用可能です。 - 見た目:
• 光を透過し、自然な歯のような透明感を持つため、非常に美しい仕上がりが得られます。また、色や形を個々の患者に合わせてカスタマイズできます。 - 接着技術:
• 高度な接着技術・材料を用いることで、ラミネートべニアが歯にしっかりと固定されます。これにより、外部からの影響を受けにくくなります。 - 適応範囲:
• 歯の変色、軽度の欠損、形状の不整、咬合不全など、さまざまな見た目の問題に対応可能です。 - 最小限の侵襲:
• 基本的にエナメル質内に限局されるため、歯を削る量が極端に少なくなります。そのため虫歯になりにくく歯の健康を保ちながら審美的な改善が図れます。 - メンテナンス:
• 特別なメンテナンスは不要ですが、通常通り、当該歯を含めたお口の中の定期的な検診や適切な口腔衛生が推奨されます。
【ポーセレンラミネートべニアの適応症・禁忌症】
ポーセレンラミネートべニアの適応症と禁忌症について詳しく説明します。
【適応症】
ポーセレンラミネートべニアは、以下のような症状や状態に対して適用されます。
- 歯の変色:
• 内因性または外因性の変色があり、ホワイトニングでは改善しない場合。 - 軽度の歯の欠けや摩耗:
• 軽度の欠けや摩耗がある歯を修復するため。 - 歯の形状不良:
• 不揃いな形状やサイズの歯を整えるため。 - 隙間のある歯並び:
• 歯と歯の間に隙間がある場合、ラミネートべニアで整えることができます。 - 咬合の改善:
• 咬合のバランスを整えるための補助的な手段として。 - 審美的な改善:
• 美しい笑顔を実現するための審美的な目的。
•
【禁忌症】
ポーセレンラミネートべニアが適用できない場合や慎重に行うべき状態は以下の通りです。 - 重度の歯周病:
• 歯周病が進行している場合、治療が必要です。 - 重度の虫歯:
• 虫歯が深刻な場合は、まず虫歯治療が優先されます。 - 不適切な咬合:
• 咬合が不適切で、強い力がかかる場合は、ラミネートべニアが破損するリスクがあります。 - 歯の強い摩耗や欠損:
• 歯が大きく欠けている場合や、根の状態が悪い場合は、ラミネートべニアが適用できません。 - 不適切な口腔衛生:
• 十分な口腔衛生が保たれていない場合、ラミネートべニアの寿命が短くなる可能性があります。 - アレルギー:
• 使用される材料に対するアレルギーがある場合は、事前に相談が必要です。
•
まとめ
ポーセレンラミネートべニアは多くの審美的な問題に対して有効ですが、適応症と禁忌症を理解し、適切な診査を行うことが重要です。治療の前に歯科医師と十分に相談し、最適な治療法を選択することが推奨されます。
ポーセレンラミネートべニアの特徴について詳しく説明します。
【ポーセレンラミネートべニアの特徴】
- 薄さ:
• ポーセレンラミネートべニアは非常に薄く、通常0.5mmから1mm程度の厚さです。これにより、歯を大きく削ることなく装着できます。 - 素材:
• 高品質なセラミック(ポーセレン)を使用しており、自然な歯の色や質感に近い仕上がりが可能です。 - 美的特性:
• 光を透過し、自然な歯のような透明感を持つため、非常に美しい仕上がりが得られます。色や形を個々の患者に合わせてカスタマイズできます。 - 耐久性:
• ポーセレンは強度が高く、摩耗や変色に対する耐性があります。適切なケアを行えば、長期間にわたって使用可能です。 - 接着技術:
• 高度な接着技術を用いることで、ラミネートべニアが歯にしっかりと固定され、外部からの影響を受けにくくなります。 - 最小限の侵襲:
• 歯を削る量が少ないため、歯の健康を保ちながら審美的な改善が図れます。 - 適応範囲:
• 歯の変色、軽度の欠け、形状の不整、咬合不全など、さまざまな審美的問題に対応可能です。 - メンテナンス:
• 特別なメンテナンスは必要なく、通常の歯磨きや定期的な歯科検診で十分です。